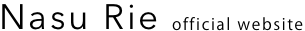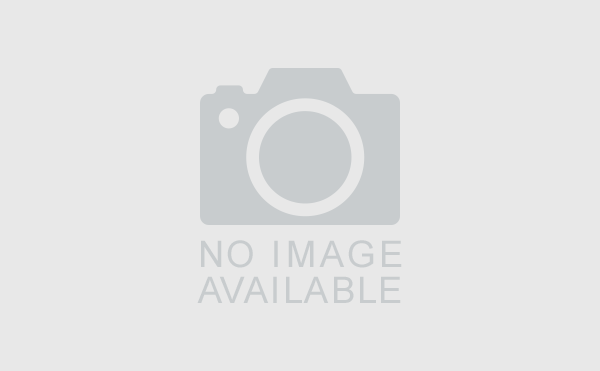103万、106万、130万は 誰にとっての「壁」なのか
103万、106万、130万は 誰にとっての「壁」なのでしょう
■働く側から見ると
103万以上働く→所得税がかかり
106万以上働く→社会保険への加入が義務付けられ
130万以上働く→扶養の枠を外れます
働くほど負担が増えますから、働くのを控えている と言えないこともありません
103万を超えて働くということは、そこに時間と労力を割くことになりますから、
税や社会保険料だけで無い働く・働かないの理由もあると思います
103万未満で働く従業員を雇う企業からみると
従業員が106万以上働くと、社会保険料を負担しなければなりません
103万円以内で働く多くが、女性や高齢者で
雇う企業も、中小企業が少なくありません
新たな法定福利費の負担は、企業、中でも主に、中小企業等の経営を圧迫することになります
さらに
103万未満で働く妻の、夫を雇う企業から見ると
妻の分の社会保険料=第三号被保険者分を負担しなくて良くなります
の「103万未満で働く従業員を雇う企業」と比較し、こちらは、大企業などが多いと思います
■
を合わせてみると、それぞれ、悲喜こもごもで
実は、103万の壁問題の背景には
第三号被保険者をどうするか、という実に大きくて深刻な問題があることが見えてきます
そして、これは、
賃金、社会保険、年金を
世帯単位で考えるか、個人単位で考えるか、
と言う問題です
「夫婦とこども二人が標準世帯は古い」といわれるのは
「世帯(家族)単位は古い、個人単位に変えよう」だけではなく、
賃金や、社会保険や、年金制度をどうするか、という
極めて政策的な問題なのです。
_____
ここからが重要なのですが、
世帯か個人か、と言っているので
個人を縛る封建的家族制度か、個人を尊重する自由な社会か
に問題をすり替えられかねませんが、
賃金、社会保険、年金などの仕組みを
世帯単位にするか、個人単位にするか
が、問題の本質です
103万の壁で、税制は、一歩、個人単位に近づきましたが
課税や社会保険料負担ばかりが、個人になり、
肝心の賃金、社会保険・年金の給付は、
個人には程遠い状況です
なぜ 103万の壁問題は
賃金、社会保険、年金等を、個人型にするための 通過点です。みなさんどうしますか?
と言わないのでしょう
なぜ、議論で、
賃金をあげ、年金・医療・介護などの社会保障給付を拡充するのが先決だ!
という議論にならないのでしょう
私は、世帯単位か個人単位かは、
十分な賃金=適正な労働分配
十分な社会保険給付=企業の法定福利費の相応の負担
が実現してからの議論だと考えています
このままの制度で進めば
ほんの一握りの超富裕層と、一握りのほどほど層と
それ以外の多くの低所得者層の社会になっていくでしょう
世帯単位で、個人を尊重することもできますし
個人単位で、権利が脆弱な最悪の社会をつくることも可能です
シャウプ勧告以来、
日本の所得税・個人住民税において個人課税を基本としつつ
扶養控除・家族の構成に応じたしくみもある、
と大田区も答弁しています。
それが、森喜朗総理の時の2000年の男女共同参画審議会の答申で
世帯単位の考え方を持つものについては個人単位に改めるなど
「必要に応じ」制度の見直しを行うべき
と言う方向性が示されています。
この世帯単位の考え方の事例として
・夫婦同氏制など家族に関する法制
・配偶者に係る税制
・国民年金制度における被用者の被扶養配偶者(第3号被保険者)
・遺族年金の在り方や夫婦間での年金権の分割
・健康保険制度における被扶養配偶者(介護保険制度の第2号被保険者を含む)の扱い
・税制や社会保障制度の所得限度額を目安として決められることがある企業の配偶者手当
などが挙げられています。
これらについて、答申は、
個人のライフスタイルの選択に大きなかかわりを持つものについて、
個人の選択に対する中立性の観点から総合的に検討
と言っていますが、
世帯か個人化を中立性の観点から検討することは
トレードオフ
のように思います。
どちらかにすれば、どちらかを選ぶことで、不利になる、ということです。
実際、
個人単位になってきたことで、家族単位で支えてきたアンペイドワーク部分は
政府も、企業も、払ってくれるわけでは無く、
自己責任=つまりは、個人の所得の中で、負担してきたということでしょう。
答申の言葉通りになっているか、
与党・行政は、守る責務を負っていると思いますし
野党は、しっかりと追及していただきたいものです。