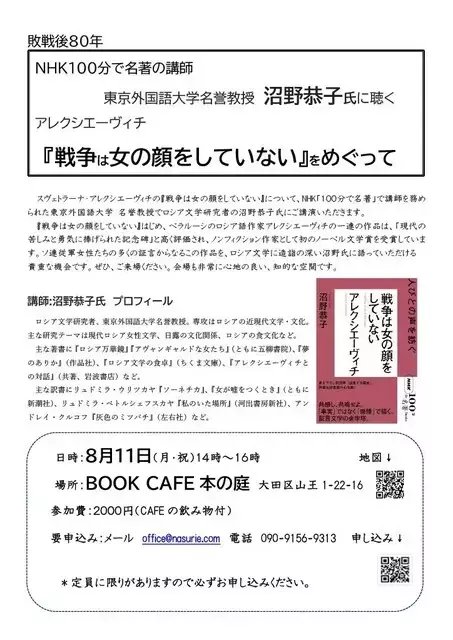NHK100分で名著の講師 東京外国語大学名誉教授 沼野恭子氏に ロシアの作家、アレクシェーヴィチの「戦争は女の顔をしていない」についてのご講演をいただきました。
「戦争は女の顔をしていない」は、2015年にノーベル文学賞を受賞しています。
数百人の、名もなき小さな証言を元に書かれた、この小説の受賞により、文学の定義が広がったと沼野先生は指摘されています。
支配者、権力者の考えや戦略ではなく、
普通の人、
どちらかというと「弱者」がどう感じたかを語る声に耳をすまし、
普通の人々の感情の歴史を綴ってきたのが、「戦争は女の顔をしていない」です。
私は、沼野先生のご講演を通じ、小さな声に耳を傾けることの重要性について、あらためて、想いをよせました。
たとえば、アレクシェーヴィチからインタビューを受けることを知った夫は、
妻が恋愛のことを話すのが好きなのを知っているから、
妻に「戦争のことを話すんだぞ」と言って、二日がかりで教え込んだりします。
(戦場の恋愛を話したい妻の)小さな声は、
(戦争を良く知る?)大きな声(どこに何ていう戦線があったか、どこに味方がいたか)に、かき消されがちですし、
小さな声の持ち主は、自分の話したいことに、どれほどの価値があるのか、気づいていないことも、多いと思います。
夫のいいつけをメモに取って話そうとする妻が、
それでも、
好きな恋愛の話、
・一晩かかって包帯のガーゼで花嫁衣裳を縫い上げたことや、
・靴までは間に合わなくて軍用長靴だったことを、
・嬉々として話すのは、
アレクシェーヴィチという「優れた聞き手」を前にしていたから、でしょう。
それは、この、インタビューのシーンの、
「あら、何を笑っているの?あなた、なんていい笑い方なの?」と記された、
妻の声に表れている、と沼野先生は、私たちに教えてくださいます。
小さな声は、
価値を与えられていないこともあって、顧みられないし、
声を上げる場(機会)が、そもそも少ないうえ、
大きな声に妨げらたり、影響されたりします。
小さな声が、自分の声で語れる環境を作ることの大切さを、改めて認識しました。
アレクシェーヴィチの「亜鉛の少年たち」という著書の
息子が戦死し、小窓も無い金属の箱に入れられて運ばれてきて、絶望に暮れてその箱に縋り付いていたはずの母親たちが、
国際友好の義務や、国益やなどを信じ、
壇上に上がって少年たちに『国のために義務を果たそう』と呼び掛けている
と言う部分を引用は、
小さな声は、大きな声に影響され、
影響されるどころか、自己検閲まで、することがあるということ、
を教えてれます。
小さな声に耳を傾けるには、
ただ聴くのではなく、
大きな声からの影響や自己検閲を取り除いた、環境整備が必要だということです。
それが、政治で言えば、
フェアな民主主義、
です。
選挙と多数決だけで、フェアな民主主義は、守れない
沼野先生は、ほかにも、たくさんの気づきを与えてくださいました
ぜひ、沼野恭子先生が解説していらっしゃる
NHK100分で名著「戦争は女の顔をしていない」
そして、アレクシェーヴィチの
「戦争は女の顔をしていない」
お読みください