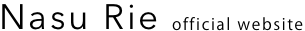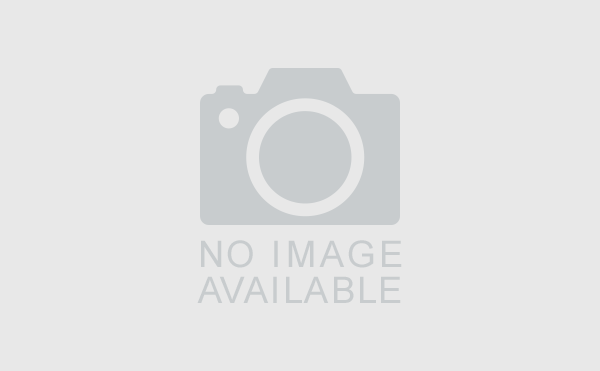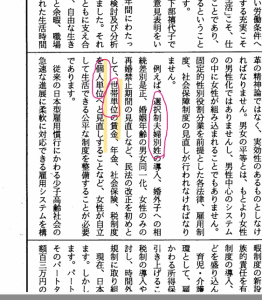まだ間に合うか、遅すぎたのか~同床異夢の地方分権・行政改革~
2003年に議員になって、もう20年以上が立ちました。
議員になったばかりの頃は、地方分権は、良いことだと思っていました。
それが、少しして、地方分権の理念は良いことだけれど、理念通りになっていないことに気づきました。
考えてみれば、中央集権で、主権者の声を聴かない政治が、単に、地方に権限がおりて地方分権になったからと言って、主権者である住民の声を聴くようになるわけが無いのです。
それどころか、地方分権を名目に始まった特区で、規制緩和が進みました。
少しなら、便利になるから、と言って、規制の手を緩めたのです。
規制は、権力を縛りますが、その縛る手を緩めたので、力のあるものの力がより強くなりました。
地方分権の旗振り役だった、故西尾勝先生は、「自治・分権再考:地方自治を志す人たち」の中で、こう指摘しています。
分権を進めてほしいという点では共通であったものの、政界・財界が望んだことは、行政改革の一手段としての分権だったということである。小泉改革において、典型的に現れたように、「官から民へ」、そして「国から地方へ」というのが行革の柱で、地方分権改革は、この行革の一環として位置づけられたものでしかなかったのである。
(自治・分権再考:地方自治を志す人たちへ/西尾勝著/ぎょうせい)
先日、減税を学びに、名古屋市の視察に行って、総務省が、減税した自治体に、行政改革を義務付けていることを知りました。
ここでも、行政改革です。
あらためて、行政改革について調べたら、第89代 橋本 龍太郎 内閣総理大臣の平成9年(1997年)に、行政改革会議の最終報告が出ていました。ここで、日本の統治機構を抜本的に変えることになる、行政改革の方向性が定められていたのです。
私が議員になったのが、2003年当時、既に、この国の方向性が形づけられていたわけです。
出されてから30年近くが経過した
最終報告には、こう書かれています。
21世紀の日本にふさわしい行政組織を構築するには、まず、国家行政の機能とその責任領域を徹底的に見直すことが前提となる。
-
「官から民へ」、「国から地方へ」という原則がその基本とならねばならない。
-
規制緩和や地方分権、官民の役割分担を徹底し、民間や地方にゆだねられるものは可能な限りこれにゆだね、行政のスリム化・重点化を積極的に進める必要がある。
-
今日、公共性の空間は、もはや中央の官の独占物ではなく、地域社会や市場も含め、広く社会全体がその機能を分担していくとの価値観への転換が求められている。
そして、ここから、アウトソーシングと効率化へと導かれていきます。
ねばならない
必要がある
価値観への転換が求められている
官から民へ、国から地方へ、価値観の転換は、誰が、ねばならぬ・必要と考え、私たちにその価値観を求めたのでしょう。
官から民へ、国から地方へ、価値観の転換で、私たちは、地方分権の目的でもあった、豊かでゆとりある暮らしを手に入れられたでしょうか。
それが仮に、誤りだと気づいたとき、私たちには、それを改善する余地があるのでしょうか。